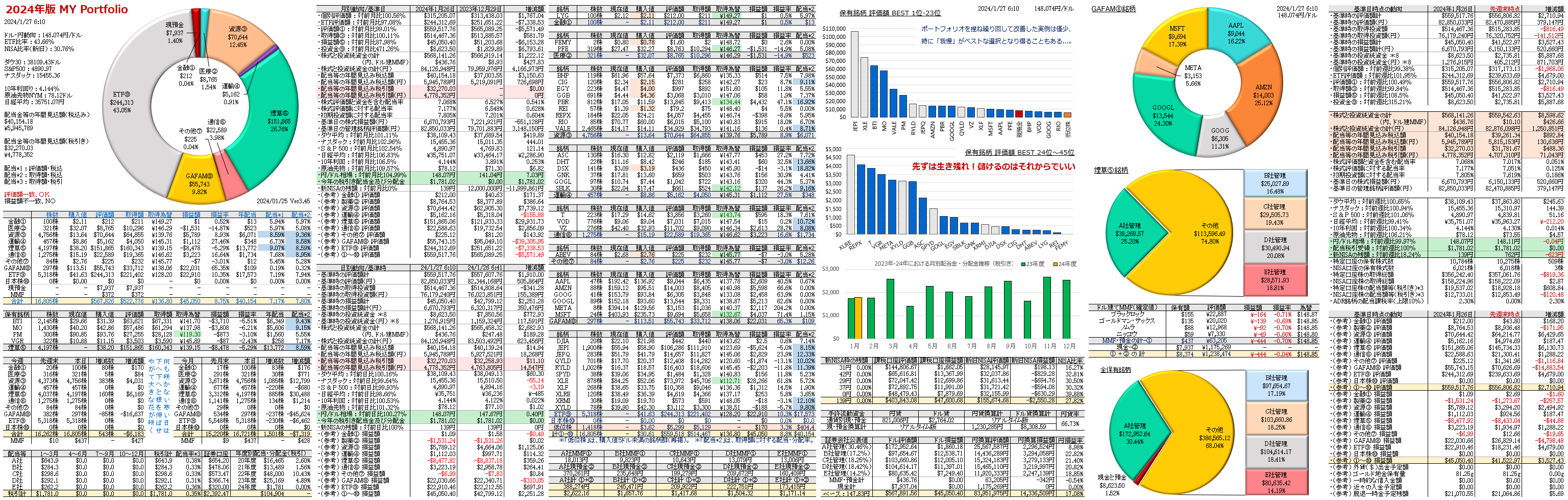【有益な記事】弱い米雇用、背後で生産性回復の兆しか?
米経済は活況なのか、それともリセッション(景気後退)の瀬戸際にあるのか。正直なところ、どちらの見方も成り立ち得る。
アトランタ連銀が採用するモデルの予測によると、経済生産の最も広範な指標である実質GDP(国内総生産)は、7-9月期に年率3.8%という猛烈なペースで成長した。
しかし、雇用と労働時間は6~8月の3カ月にわたり、ほとんど増加しなかった。9月のデータは政府機関閉鎖のため、予定された3日に発表されなかった。米民間雇用サービス会社ADPは、9月の民間就業者数が減少したと推計している。
GDPと雇用関連統計が異なる方向に動くことは実際に時折あるが、これほど大きく乖離(かいり)するのはまれだ。
幾つかの説明が考えられる。第1に、GDPを構成する消費、投資、貿易のデータのほか、雇用データが過去数カ月にわたり誤っており、修正される可能性がある。
第2に、このずれは異常であり、恐らくGDP伸び率の鈍化、もしくは雇用の増加、あるいはその両方を通じて解消されるだろう。ルネサンス・マクロ・リサーチのエコノミスト、ニール・ダッタ氏は、個人消費は持続不可能な貯蓄率低下によって支えられており、クレジットカードのデータによれば、9月には既に軟化しているとの見方を示した。
第3の可能性が最も興味深い。生産性向上が進行しているかもしれず、それは米経済が今後数年間、インフレが抑制される中でより高い成長率を達成できることを意味する。
経済生産が増えたものの、労働時間は増えていないため、時間当たりの労働生産性は年率約3.5%と、堅調なペースで伸びた。
GDPと雇用が異なる方向に動き続ける可能性は低いため、生産性の伸びが続く可能性も低い。それでも、7-9月期の推測を含め、生産性はここ2年間、年率で約2%伸びている。それは新型コロナウイルス流行前の10年間に見られた1~1.5%を上回っており、何かが起きていることを示唆する。
その何かとは、テクノロジーに関係する公算が極めて大きい。あり得るのは、チャットGPTなど、大規模言語モデル(LLM)によって具現化された生成AI(人工知能)だ。これらの利用が始まってから3年もたたないが、普及のスピードは目を見張るほど速い。調査会社ギャラップは6月、米国で働く従業員の19%が1週間に数回以上AIを使用していると述べた。ウォルマートは最近、向こう3年間にわたり全体の従業員数を横ばいに保つとの意向を示した。同社のダグラス・マクミロン最高経営責任者(CEO)はAIが「文字通りすべての仕事」を変える可能性があると述べた。
それでも、電気やコンピューターがビジネスと経済を変革させるのには何十年もかかった。AIについても同じことが言えるかもしれない。
マサチューセッツ工科大学(MIT)のAIプロジェクト「ナンダ(Nanda)」が発表した、広く引用されている報告書によると、調査した52の組織の95%は、AIの取り組みから全く利益を得ていない。これは、AIが経済全体の生産性を向上させる上で、まだ十分なインパクトをもたらしていないことを示唆している。
しかしLLMへの投資は、電子商取引、ソフトウエア、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、機械学習などへの現在の投資を基盤として積み上げられている。ゴールドマン・サックスの最近の分析によれば、科学研究、工学、コンサルティングといったハイテクとそれに関連する分野が、生産性の伸びの中心になっている。また、最も急速に成長している「スーパースター」企業の間で特に、生産性の伸びが顕著だという。
ゴールドマンは「生産性の伸び加速の要因をすべてAIに帰するのは恐らく時期尚早だが、AI技術を最も積極的に活用している事例の幾つかは、こうした業界で見られる」と指摘している。
オラクル、アマゾン・ドット・コム、メタ・プラットフォームズなどの企業による、AI事業に必要な半導体、データセンタ-、発電などへの巨額投資は、多くの人々からバブルのような状況だと見なされている。しかし、たとえバブルであってもそれは、生産性の面で真の恩恵をもたらすかもしれない。
それは1世代前のインターネットテックブームの際にも、間違いなく真実だった。シティグループのエコノミストらは最近、インターネットとAIという二つのブームの比較を試みた。インターネットのブームは、ネットスケープの新規株式公開(IPO)と、全米科学財団(NSF)のネットインフラの完全商業化が実施された1995年に始まった。
シティによると、このブームの最初の5年間のインターネット関連投資額は、年平均でGDPの1.25%というすさまじい伸びを記録した。1995~2004年の年平均の生産性伸び率は、それ以前の20年間の倍に当たる2.9%に達した。国民1人当たりの所得が倍増するのに以前は47年かかったが、こうした高い生産性の伸びが続けば、それが24年で達成できることになる。GDP伸び率は年率3.3%に押し上げられた。
シティの推計によると、AI設備投資額は2023年以降、年平均でGDPの0.9%分の伸びを記録している。この伸び率は、1995~2004年のインターネットブームにおける同様の期間の伸びを上回る。
シティのグローバル担当主任エコノミスト、ネイサン・シーツ氏は、GDPの伸びはAI投資の需要サイドの刺激によって押し上げられているのであり、供給サイドの生産性向上によるものではないと指摘する。それでも、シティによれば、現在のAI投資をインターネットブーム時代に照らし合わせると、「今後数年のうちに」生産性の上昇が起きる可能性があるという。
複数の学者が、AIによって自動化可能な業務量とそれによるコスト削減効果を測定することで、AIの生産性向上効果を試算している。シティはこれらの試算から、AIが押し上げる生産性の伸びは年間0.5~1.5ポイントとみている。つまり、最も強気なシナリオの場合以外はインターネットブーム時を下回る。
これは、経済成長の伸びを促進するだけでなく、企業の人件費削減によってインフレに対する下押し圧力にもなり得る。だが、ドイツ銀行のエコノミストによる最近のリポートでは、こうした見通しに悲観的な見方が示されている。
同リポートによれば、1990年代のテック主導型の生産性向上は唯一のインフレ抑制要因ではなかった。当時はまだベビーブーム世代と女性の労働市場への大量流入が続いており、それが労働力の供給を押し上げていた。冷戦の終結や北米自由貿易協定(NAFTA)の発効、関税貿易一般協定(ガット)ウルグアイ・ラウンドによって貿易障壁が低減されたため、物価上昇が抑えられた。
ドイツ銀行のエコノミストは「米経済の脱グローバル化への転換が、こうした過去のディスインフレを覆すだろう」と予想。その一方で、「世界的な高齢化と移民流入の減少(中略)が米労働市場の引き締まりにつながり、構造的にコスト圧力が上昇することになる」と指摘した。
現在のデータが示す難問のもう一つの側面、つまり軟調な労働市場と生産性の向上がインフレ抑制にそれほど寄与していないという状況は、そのような脱グローバル化への転換によって説明できるかもしれない。(ウォール・ストリート・ジャーナル)――筆者のグレッグ・イップはWSJ経済担当チーフコメンテーター
編集後記
トランプ関税派の賦課は、米国内のインフレを助長すること以外、用をなさないという論理が反トランプ派のアナリスト達をを中心に罷り通っていましたが、米国個人投資は「これらを完全に無視」して、ひたすら米株買い突き進みました。今、これが結果となっています。